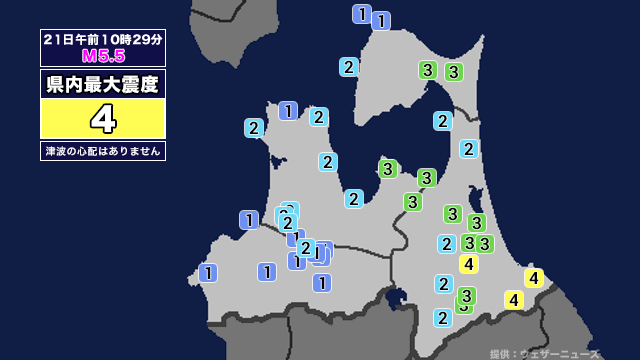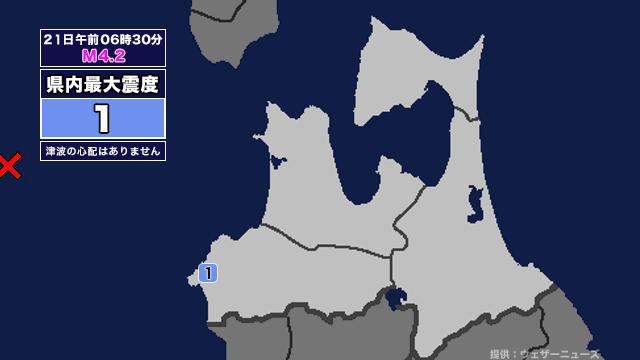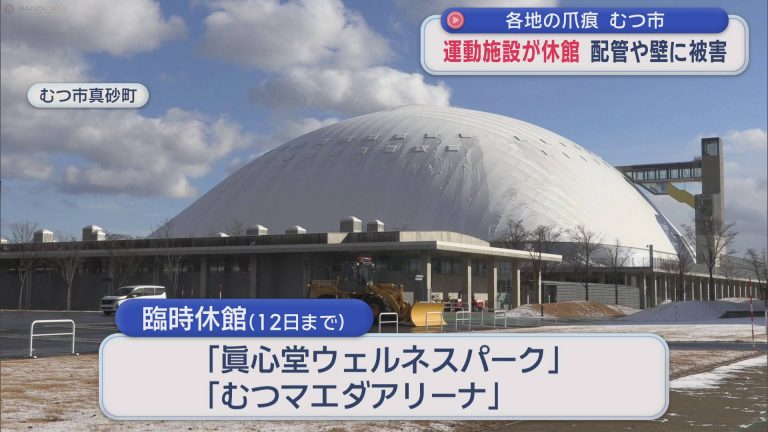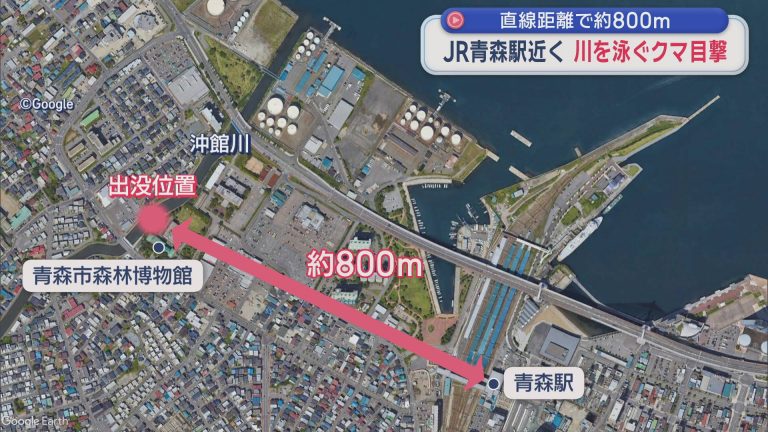ANNでは、参院選について、公示日から16日のXのすべての投稿について分析ツールを使って調べました。
その中で、青森選挙区に関連するキーワードの上位10個を並べました。
候補者の名前や政党名がありますね。中でも、参政党関連は5つと半数を占めました。
候補者を知るうえで欠かせないツールとなっているSNS。各候補者もSNSを使って活動の様子を発信していますよね。
一方で専門家は「攻撃的な要素が強まる」危険性について指摘しています。
【自民党 神田潤一衆院議員】
「せーの、もとめちゃ~ん!よろしくお願いします」
自民党の現職・滝沢求さん。応援弁士たちが親しみを込めて呼ぶ「もとめちゃん」というワードが、Xの全量分析でも一時トップ10にランクイン。
3期目を目指す滝沢さんですが、SNSを駆使しての選挙戦は今回が初めて。YouTubeでは毎日午後7時にショート動画を投稿しています。その狙いは…。
【自民・現 滝沢求候補】
「どちらかというと私は堅く見られるかもしれない。素のままの滝沢を発信していくのも一つかなと思って」
「(SNS)見てますよと声をかけてくれる方もいらっしゃるので、一定の効果があると考えております」
【立憲・新 福士珠美候補】
「上のほうがいい」
街頭演説の直前、動画撮影の場所を探す立憲民主党の新人・福士珠美さん。カメラワークを提案します。
元アナウンサーの経験を生かし、リポート風の動画を撮影。今回のポイントは…。
【立憲・新 福士珠美候補】
「ずっとこれでいくより、画変わりしたほうがいいじゃないですか」
実際の投稿画面です。
参院選出馬前から自身の活動をSNSに投稿し、発信していた福士さん。選挙活動としてのSNSの活用について、これまでとの違いは…。
【立憲・新 福士珠美候補】
「全然意識していない、行った先々で撮れるなと思ったら撮る」
撮影に慣れている人はこちらにも…。
参政党の新人・加藤勉さんは、各地での活動の様子を自撮りでPR。
【参政・新 加藤勉候補】
「自撮りは毎日、自撮り大好きというか、自撮りのほうが伝わると私は思っている」
SNSでの拡散で全国的に支持が拡大している参政党。Xの全量分析でも参政党関連のワードが上位を占めました。
【参政・新 加藤勉候補】
(Q.SNSの拡散力について)「それはすごいものがある。だから間違ったことはもちろん言えないし、消しても消えないし、そこは慎重にしています」
共産党の新人・荻野優子さん。1日に3回以上はSNSを更新できるように意識しているといいます。特に反応があるのが演説スケジュールの告知です。
【共産・新 荻野優子候補】
「若い世代から『SNSで見てきょうここで演説するって聞いたから来た』と言ってもらえることも増えてきているので、ツールとしては今後も大事なものになっていくのかなと感じている」
政治団体NHK党の新人・佐々木晃さんも、自身のXアカウントで今回の選挙に関わる内容をいくつか投稿していました。
今回の参院選について、投票先を選ぶ際に何を参考にするかANNが行った世論調査では、「テレビ」が68%、「新聞」が60%となった一方、「SNSや動画サイト」は32%にとどまりました。
一方で青森大学の学生に取ったアンケートでは「SNS」を情報源としている学生が7割以上というデータも。
情報収集には欠かせないツールとなっているSNS。投稿の中には第三者が候補者の発言などを短く切り取り、より印象に残るよう編集された動画もあります。いわゆる「切り抜き動画」です。
元新聞記者でメディア論に詳しい青森大学社会学部の櫛引素夫教授は、この「切り抜き動画」の危険性についてこのように話します。
【青森大学社会学部 櫛引素夫教授】
「いろいろな脈絡の中での発言の一部分だけを切り取って、批判や中傷の材料にしようとする場合は、攻撃的な要素が強まる」
SNSの投稿をイメージした画面です。
【藤原祐輝アナウンサー】
「ニュースなんて全然見ない、むしろ嫌い!」
動画には、「藤原アナはニュースが嫌い。キャスターにふさわしくない」というコメントが添えられています。
しかしこの発言の前後を見てみると。
【藤原祐輝アナウンサー】
(Q.キャスターをやっていてうれしかった時)「この前ある方から『昔はニュースなんて全然見ない、むしろ嫌い!と思っていたけど、ABAを見るようになってニュースが好きになりました!』と言われた時ですね~」
全く別の内容ですが、意図的に発言を切り抜くことでネガティブな印象を与える投稿になりました。
【青森大学社会学部 櫛引素夫教授】
「相手に対する批判とか攻撃的な言葉が、どうしても負の連鎖を呼びやすい側面がある」
「情緒的な刹那的な感覚で、ワッと広がる状況がかなり危うさを伴っていると感じます」
SNSの発信の仕方 1 つとっても、その候補者のパーソナリティが見られるような感じがしますけれども、一方で切り取られている可能性があるということも視野に、私たちは見抜く力も必要になってきますね。
櫛引教授は発言を切り取るというのは、テレビも同じであるというふうに話していました。
私たちは、発言を要約すると分かりやすくはなるけれども、要約するとディテールが損なわれるというジレンマを抱えながら、限られた放送時間の中でニュースをお伝えしています。
私たちは今後も丁寧な資材に基づく、分かりやすいニュースをお伝えできるように努めてまいります。
※Xの分析の調査期間は「7月3日~16日」です。画面の表記に一部誤りがあり、訂正・お詫び申し上げます。